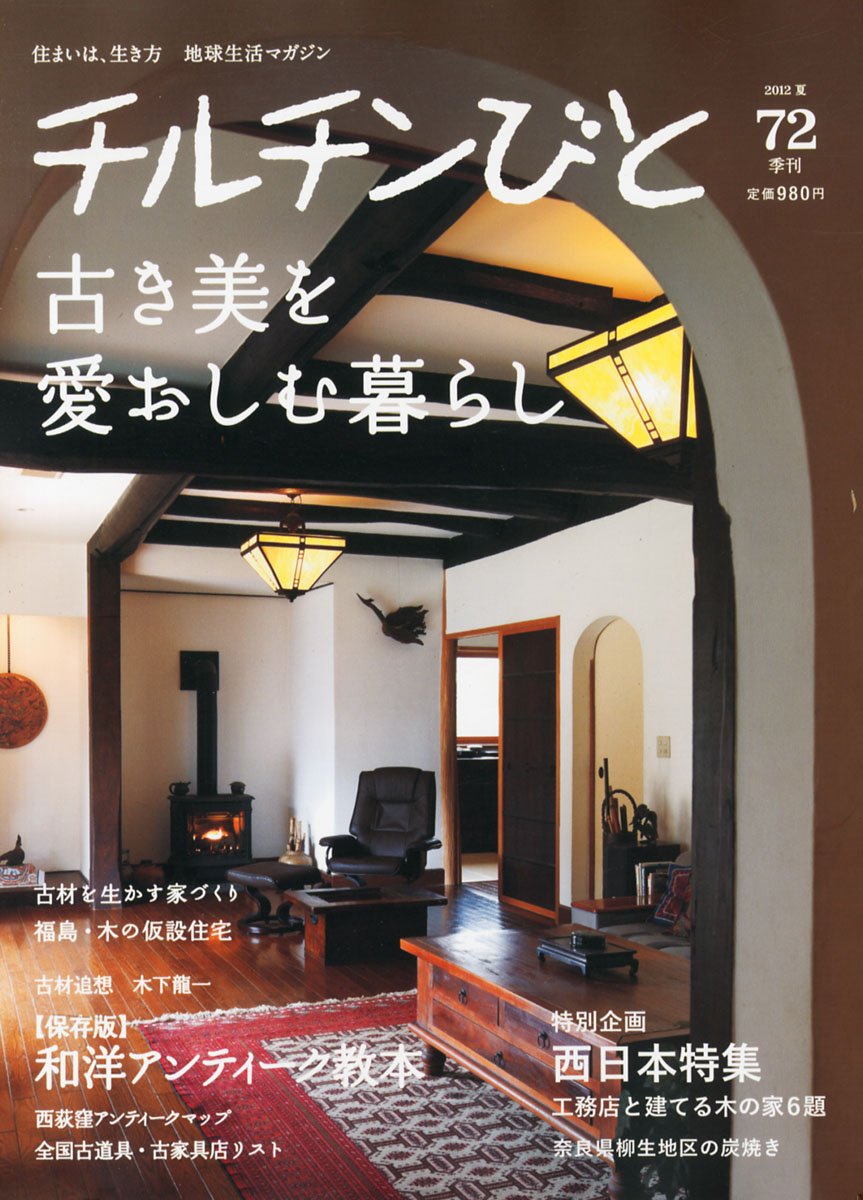木造住宅の寿命|リノベーションで実施できること

国土交通省の資料では、早稲田大学の小松幸夫氏らによる建物の平均寿命実態調査データの一部が抜粋されています。当資料によると、木造住宅の平均寿命は約65年(※2011年調査)。
出典:国土交通省「中古住宅流通促進・活用に関する研究会 参考資料」
出典:小松幸夫(早稲田大学)「建物の寿命と耐用年数」
ですが実際は一般的にリノベーションを検討し始めるのは築20年頃から、建て替えを検討するのは築30年頃だと言われています。
もちろん築20年なのに基礎部分がガタガタになっていたり、シロアリのトラブルがある住宅もあれば、築30年でもまだまだしっかりしている建物もあるでしょう。築年数はあくまでも目安です。
そもそもリノベーションとは、既存物件の設備や機能を刷新し、より高い価値を生み出すための改修工事のことです。リノベーションの実施によって、標準的な寿命を超えて家に住み続けることができます。
また、リノベーションに伴い耐震性や断熱性・気密性を高めることで、安全かつ快適に過ごせる住宅も実現でき、結果として住宅寿命を伸ばすことにもつながるでしょう。住み慣れた愛着のある家で暮らし続けたいなら、リノベーションは非常におすすめの選択肢と言えます。
木造住宅のリノベーションでは、下記の施工を実施することが一般的です。
- 間取りの変更
住宅の構造部分はそのままに、間取りだけを変更する方法です。水回りの設備を1階に集約させたり、子ども部屋をなくして広いLDKスペースを確保したりするなど、変更パターンは千差万別となります。
- 外観の変更
築年数の古い木造住宅の場合、塗装の剥がれなど外観の老朽化も目立つケースが多々あります。リノベーションで外装デザインを新たに変更したり、耐震・耐火性能を向上させて自然災害の被害に備えたりなど、施工内容もさまざまです。
- バリアフリーへの対応
住み慣れた家で老後も安心・安全に暮らすため、バリアフリー住宅へのリノベーションを行う方も多くいます。耐震性や耐火性の向上はもちろん、室内の段差をなくしたり階段やトイレに手すりを設置したりなど、バリアフリー化できる箇所は多くあります。
木造住宅で「リノベーション」と「建替え」を判断するには?
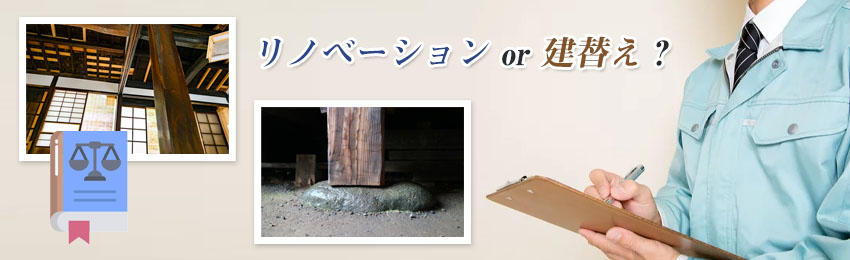
木造住宅の状態によっては、リノベーションではなく建替えが望ましいケースもあります。建替えとは、既存住宅を基礎部分から取り壊し、一度更地にしてから新たに住宅を建て直すという方法です。住宅構造体そのものをすべてやり直す大規模な工事内容となるため、リフォーム費用・リノベーション費用よりも建替え費用のほうが高くつくと想定できます。
老朽化が進んだ木造住宅の場合、基本的には建替えが最もおすすめです。しかし、下記のような要望がある場合は、リノベーションがベストな方法と言えるでしょう。
いくらリノベーションで耐震性や断熱性を向上させられるとは言え、性能は建替えに劣ります。コストを抑えたい場合、性能は妥協してリノベーションを実施することがベストです。
建替えは新たに住宅を1から建て直すこととなるため、これまでその家で過ごした思い出をなくしたくないという方や、お金をかけてでも建物を残したいという方は、建替えではなくリノベーションが適切です。 |
上記のような要望が特にない場合、基本的にはその道のプロフェッショナルである工務店やハウスメーカーに問い合わせて相談することで、現状に適したベストな選択につながります。
ここからは、リノベーションと建替えを判断する上で、最低限確認しておきたいポイントを紹介します。
住宅の土台を確認する
老朽化した木造住宅のリノベーション・建替えを判断する最も重要な基準が、住宅の土台です。大規模に住宅の土台部分に問題がない場合は、何がなんでも建て替えしなければならないということはありません。性能を追い求めない、あるいは建物の雰囲気を残したいのであれば、リノベーションも十分に検討に値するでしょう。
住宅の土台の状態は、ひび割れや変色などでも判断できますが、知識のない方が簡単にチェックできるものではありません。建築士などの専門家に住宅診断を依頼して、しっかりと診断してもらいましょう。
住宅の柱・梁を確認する
住宅の柱や梁もチェックポイントの一つです。柱・梁を確認するときは、土台と同様、木材が腐敗していないか・シロアリ被害が発生していないかをチェックしましょう。
住宅の基礎部分に大きな問題がなくても、多くの柱や梁にこれらの問題が見られた場合は、安全性や耐久性に大きく欠けます。万が一、台風や地震などの自然災害による被害を受けると、破損や崩壊のおそれがあるため、リノベーションではなく建替えを行う方が望ましいと言えるでしょう。
法律・条例を確認する
築年数の古い木造住宅は、建築当時から現在までに法律・条例が変更されたことによって、建替えのできないケースもあることに注意が必要です。このような住宅は、「再建築不可物件」「セットバック要物件」などにあたります。
再建築不可物件やセットバック要物件で、どうしても建替えをしたい場合は、既存よりも建物面積を小さくしたり、隣接する土地を購入して建替えのできる条件をクリアしたりしなければなりません。建替えのできない木造住宅であれば、リノベーションが最も現実的かつスムーズな方法と言えるでしょう。
木造住宅のリノベーションを行う場合の注意点4つ

木造住宅のリノベーションには、いくつかの注意点があります。特に注意すべき点は、「建替えよりも安く済むと思って工事を始めても、場合によってはむしろ高くつく可能性がある」という点です。加えて、間取りに関する希望があっても、土地の形状や広さによっては実現できないケースがあることも覚えておきましょう。
ここからは、木造住宅のリノベーションにおけるさまざまな注意点を具体的に説明します。
電気・水道関連の工事が必要になる場合がある
築年数が古ければ古いほど、住宅そのものだけでなく、ライフラインをしっかり確保するための設備工事も必要となる可能性が高まります。目に見えない部分となるため見落としがちですが、設備工事もしっかりと予算に組み込むようにしましょう。
また、リノベーションに伴い、IHキッチンにしたり浴室乾燥機を導入したりしたいという方も多くいます。当然、新たな住宅設備を追加する場合も電気配線工事が必要です。
これは電気関連だけでなく、水道関連も同様です。キッチンやお風呂場、洗濯機置き場など、水廻り設備の位置を大きく変更する場合は、給水管や排水管などの取り換え工事が必要となるケースがあることも覚えておきましょう。
補修箇所が多いほど高額化する
補修箇所が多ければ多いほど、当然コストはかさみます。特に耐震補強工事はリノベーション項目の中でも多額の工事費用が発生する項目となることを覚えておきましょう。
予算が限られている場合や、なるべくコストを抑えてリノベーションを行いたい場合は、まずリノベーションで求める住宅の強度や設備の性能を明確にしたうえで、適切なリノベーションプランを立てましょう。譲れない箇所・妥協できる箇所をリストアップしておくことで、比較的スムーズに打ち合わせを進めることが可能です。
間取りを変えられない工法がある
床・壁・天井の面で建物を支える「ツーバイフォー工法(木造枠組壁工法)」や、工場であらかじめ生産された骨組みを組み立て、同様に床・壁・天井の面で支える「プレハブ工法」の場合、基本的に間取りを変更することはできません。建物を支える重要な面である「耐力壁」を壊すことが不可能なためです。
いくつかの条件を満たすことで、多少の間取り変更工事は可能となりますが、それでもその他の工法より多くの制限がされています。まずは工法の確認をした上で、間取り変更に制限のある工法の場合はどのようなリノベーションが可能となるかを施工業者や専門家に相談することがおすすめです。
法令上の制限によって増築できない場合がある
一戸建て木造住宅は、マンション・アパートといった集合住宅に比べて土地・建物ごと専有するため、増築の自由度が比較的高いことが特徴です。しかし、すべての木造住宅が自由に増築できるわけではありません。建築基準法や都市計画法といった法令上の制限によっては、いくら土地に建物を建てられる余裕があっても増築できないケースもあります。
建築基準法や都市計画法など、住宅に関連する法令は年々改正されていることも特徴です。「ある程度のリノベーションプランを立てたにもかかわらず、法令上の制限によってプラン作成をやり直さなければならなくなった」といったことが起こらないよう、リノベーションや建替えを検討する際は、まず法令や規制をチェックしておきましょう。
まとめ
自分たちにとってリノベーションか建替え、どちらがよいかを判断するためには、さまざまな要素が関係します。住まいに関する知識がないままベストな判断を行うことは困難なため、信頼できる専門家に相談することが最もおすすめです。
木造注文住宅を主に手がける「株式会社イムラ」では、築古住宅のリノベーションも提供しております。それぞれの木造住宅の状態やお客様のご要望を伺いながら、適切なリノベーションプランを提案いたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。
| ご相談はこちら |